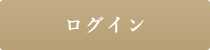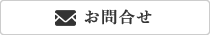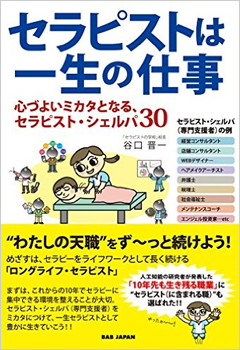- ホーム
- セラピストニュース&コラム
- 谷口校長コラム
- 遠藤基平さんのセラピストライフ~オフィスマッサージセラピスト
遠藤基平さんのセラピストライフ~オフィスマッサージセラピスト
2022/12/02
これまで16年にわたって、法人向けリラクゼーションサービスを提供している「株式会社イーヤス」の代表、遠藤基平さんのセラピストライフを紹介します。
遠藤さんが経営する(株)イーヤスでは、企業のオフィスにセラピストを派遣し、その企業に勤める従業員さんたちにボディーケアを提供しています。
現在、イーヤスには40名近くのセラピストがスタッフとして所属していて、コロナ禍以前は毎月50社ほどの企業に出向いていたとのことで、遠藤さん自身が現場に出ることもあるそうです。
イーヤスのサービスの特徴は、なんといっても企業の福利厚生の一環であることにあります。
そのため、費用を負担するのは企業であり、マッサージを従業員さんの負担はゼロか、あっても低く抑えられています。
こうした仕組みの背景には、遠藤さんの起業理念があります。
「イーヤスの理想であり、推奨しているのは、従業員さんからできるだけお金をいただかないことでした。利用率を上げたいというのが、その一番の理由です。利用率が上がるってことは、ケアを受ける人数も、機会も増えるということです。それは従業員さんにとってハッピーなことだし、それで従業員さんたちが頑張れる状態になれば企業側もハッピーになる。うまく回れば、従業員さんにとっても、企業にとっても、僕たちセラピストにとっても、とてもいい循環になるんです」(遠藤さん談)

近年では、従業員の仕事においては、労働時間よりも労働生産性を重要視すべきという考え方とともに、健康経営という考え方が広がり始めています。
従業員の心身の健康が損なわれた状態(プレゼンティーズム)にあると、業務遂行能力や生産性が低下し、それがさらに離職に繋がり、結果的に企業に不利益をもたらすという考え方です。
遠藤さんが起業したのが16年ほど前なので、日本の中では比較的に早い時期から「従業員を健康に保つ仕組み」を企業に提供し始めたといえます。
顧客が企業であり、従業員への施術代を負担するのが企業であることも、遠藤さんの取り組みの重要なポイントです。
個人でも法人でも同様ですが、経済力のある顧客を持った方が、事業として継続性が高くなる傾向があるからです。
もちろん、企業が求めるのは、従業員が健康になることだけではなくて、企業業績が良くなることです。
それに応えなければならないという点では、遠藤さんは大きなプレッシャーを感じながらも、より多くの人にセラピーに触れもらうことに力を注いでいるそうです。
こうした時代を先取りしたサービスであり、新しいセラピストの活動の仕方を生み出し、今なお模索を続ける遠藤さん。
彼がどのような経緯で今に至るのか、その歩みをお伺いしました。

「サロンが会社に来てくれればいいのにな」という言葉
遠藤さんがセラピストの世界に入ったのは、今から22年ほど前のこと。
それ以前は、法人や富裕層向けにリゾートホテルの会員権を売る企業で、営業マンとして多忙な日々を送っていました。
「大きな仕事をしてみたい」という意気込みで働き続け、年収も着実に上がっていったそうです。
ところが、ちょうど入社から5年が経った頃、当時27歳だった遠藤さんは「プチッと糸が切れたように」、後先考えずに退職してしまいます。
若さで走り続けて燃え尽きたともいえますが、それよりも金額的な仕事の大きさは、遠藤さんにとっては人生という長いスパンにおけるモチベーションには、ならなかったということかもしれません。
退職後、次の仕事を考える中で遠藤さんが決めていたのは、「次は健康に関する仕事をしよう」ということでした。
聞けば、遠藤さんには小学校1年生の頃に、生きるか死ぬかの病で長期入院していた過去があったそうです。
遊びたい盛りの時期に長く病室で過ごす経験をして、健康でなければ何もできないということが、子どもながらに心に刷り込まれたといいます。
また、営業職として多くの経営者に接する中で、何度も「お金があっても健康は買えない」という話題になったことも、「健康に関する仕事」への思いを強くさせたそうです。
そして、遠藤さんは身近な人が肩こりや腰痛に困ってマッサージやリラクゼーションサロンに行っていることに気が付き、遠藤さんはマッサージを学ぶスクールに通い始めたとのこと。
卒業後にはそのスクールが運営しているリラクゼーションサロンで経験を積みます。
遠藤さんはそこで6年半にわたって修行をし、何人もの先輩が個人サロンを作って独立していくのを見ながら、自分のスタイルを模索したそうです。
そんな遠藤さんに気づきを与えてくれたのは、何人ものお客様から受けた
「サロンが会社に来てくれればいいのにな」という言葉。
確かに、サロンが会社に来てくれれば平日に施術を受けられて、わざわざ休日に時間を割かなくてもよくなります。
それに、例えば家族との時間をなくして、自分だけリラクゼーションサロンに通うということが、心理的に気が引ける方もいることでしょう。
「個人サロンで独立開業するのは王道ですけど、自分には違和感があったんですよね。それで、“会社に来てくれると、ありがたいのに”って話を聞いて、なるほどそれもありか、と。調べてみると、海外ではメジャーな業態だったし、法人を相手に営業するのなら、営業マン時代の経験が活きるんじゃないかと思いました」(遠藤さん談)
こうした発想が、現在のイーヤスの起業に繋がっていくことなります。
「僕は、良いものはたくさんの人に伝えるべきだっていう信念があるんですよ。だから、セラピーとか、癒しとかを求めてる人はすごくたくさんいるのに、全然、届いていないっていう現状に気が付いた時に、いい施術をもっとたくさんの人に届けたいと思いました。それは僕1人ではできなくて、スタッフに協力してもらうことで出来ることも、届けられる人数も増えていくし、可能性は何倍にもなると考えました」(遠藤さん談)
遠藤さんは起業以来、「まだまだ必要な人に届けられていないし、もっと求めている人に届けたい」という思いで、これまで16年間を走り続けてきたと言います。
人生というスパンでモチベーションを維持できる「大きな仕事」を、遠藤さんは今の活動の中に見出しているのでしょう。
ここ数年は新型コロナの流行にともなって、リモートワークを取り入れる企業が増えてきました。
そのため、遠藤さんのイーヤスのビジネスモデルも難しい状況に向き合っているそうです。
実際にオンラインライブでの運動指導など、新しいサービスの試みをしているとのことですが、実際にマッサージをすることを代替するものには至らないだろうという感触を持っているといいます。

それでも、このコロナ禍での試行錯誤が、オフィスマッサージサービスの付加価値になりうるのではと、遠藤さんは話してくれました。
また、これまで関東や東海の都市部で顧客を獲得してきたとのことですが、これからは地方都市も開拓しつつ、さらに多くのセラピストや同業者と協力していくというイメージも語ってくれました。
「16年の間で多少の変動はありつつ、月の訪問現場数はずっと増えてきていたので、事業としては緩やかにですけど、順調に上がってきました。コロナ禍でリモートワークする企業が増えて不安になることもあったんですけど、まだやれるし、まだまだ必要とされているぞっていう風に思うと、モチベーションが湧いてきます。コロナ禍で気付かされたこともあるので、いろいろと可能性を追求していきたいですね」(遠藤さん談)
校長からのメッセージ
今回は、企業の福利厚生の一環としてオフィスでマッサージを提供するサービスを起業し、16年もの間、業績を伸ばし続けてきた、(株)イーヤス代表、遠藤基平さんにお話を聞かせていただきました。
働き方改革や健康経営が企業に求められるようになりつつある現在において、時代に合ったビジネスモデルだといえます。
また、セラピストの働き方として、新しい選択肢を提示しているともいえます。
セラピストの働き方としては、サロンでお客様を待つという受身のスタイルが一般的ですが、お客様のいるところに行くという、より積極的なスタイルが「出張セラピー」という方法です。
つまり、お客様の移動に掛かる時間的なコストを、セラピストが肩代わりすることでお客様が施術を受けるためのハードルを下げる方法といえます。
イーヤスのモデルは、出張セラピーよりもさらに一段ハードルを下げた仕組みが特徴的で、施術代をという金銭的なハードルを、勤める企業に肩代わりしてもらうアプローチといえるかと思います。
このモデルの面白いところは、施術を受ける人(従業員さん)の健康度合いを媒介にして、企業が最終的に利益を得ることを示していることです。
また、企業の予算に福利厚生の一部として組み込まれることで、イーヤスに、延いては出張するセラピストに安定的な収益をもたらすという仕組みも、とても大切なポイントでしょう。
企業、従業員、セラピストの3者がwin-win-winの関係性を構築することで、持続可能な仕組みとして回り続けられるわけです。
さらに言えば、企業のサービスを受けているユーザー、従業員やセラピストの家族など、社会的な規模でセラピーの恩恵を受けることになると考えれば、遠藤さんの試みは壮大な社会実験とも言えるのかもしれません。
さて、このイーヤスが提供する仕組みを考える上で、とても重要なファクターがあります。
それは、「従業員が施術を受けることによって、企業の業績が上がる」という前提があってこそであるということ。これなしにしては、企業側から求められることはないのです。
つまり、派遣されるセラピストの腕に掛かっているところが大きいのです。

企業に派遣されるセラピストに求められること
遠藤さんにスタッフに求めていることを聞くと、求めている「現場力」について教えてくれました。
「現場力」の要素の1つは、もちろん施術能力です。
イーヤスのオフィスマッサージの基本的なルーティーンを聞くと、企業での滞在時間(1〜3時間ほど)の間に、1日6〜18人ほどの方に対して、クイックな施術(15〜25分)をする、という流れになるようです。短時間集中型で、なかなかなハードワークです。
施術の成果としても、従業員さん1人ひとりの困り事をピンポイントに改善して、「良くなった」と実感してもらわなければいけないので、セラピストの腕の見せ所といえますし、イーヤスでは成果を感じてもらうための研修や情報共有にも力を入れているそうです。
「現場力」のもう1つの要素は、ビジネスリテラシーだそうです。
これは特別な能力というよりも、基本的なコミュニケーションスキルです。
気持ち良く挨拶や返事ができるか、メールのやり取りは遅滞なくできるか、聞かれたことに誠実に答えられるか、困ったことがあればすぐに相談できるか、気が付いたことを報告できるか、などなど。
言い古された「ホウレンソウ」ですが、これにつまずくセラピストは少なくないそうです。
「僕の事業を回すために重要な要素は大きくは2つあります。1つは セラピストの現場力。もう1つは企業への営業力です。営業は主に僕がやっていますが、現場はスタッフたちの力があってこそです。この両輪が上手くいくと、この事業が回っていくんですね。それが、参入障壁が低そうで高い部分なんだと思います」(遠藤さん談)
ちなみに、イーヤスに参加しているセラピストは、ほとんどがダブルワークとして取り組んでいて、個人のセラピストとしての活動と並行することで、収益の安定化に繋げているそうです。
オフィスマッサージは、多種多様な人と、その困り事に日々接することができる場としても、参加するセラピストの成長の助けになるのではないかと、遠藤さんは語ってくれました。
日本におけるセラピー業界は、医療が健康インフラであることに比べれば、同じ心身の健康に資する業態でありながら、健康インフラたり得ないのが現状です。

それでも、日々の社会活動を円滑に回すための潤滑油として、セラピーが影ながら果たしてきた役割はあるはずです。
遠藤さんのように、社会の仕組みの中に、積極的にセラピーを組み込もうとする試みをするセラピストが、近年少しずつ増えてきたように思います。
そうした活動を通して、セラピーが少しずつ社会に浸透していき、いつの間にか社会の潤滑油として、その必要性が認知される日がきっと来るのではないでしょうか。
イーヤス
オウチdeリフレッシュ