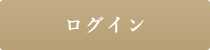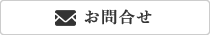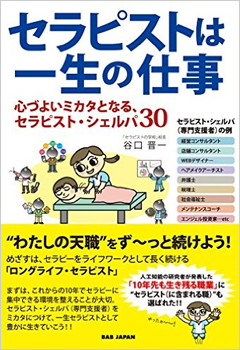- ホーム
- セラピストニュース&コラム
- 谷口校長コラム
- 木村淑子さんのセラピストライフ〜サロンセラピスト
木村淑子さんのセラピストライフ〜サロンセラピスト
2024/02/01
2015年から大阪南森町にて「salon de lumiere(サロン・ド・ルミエール)」を経営し、さらにJ-LABOという企業で施術用のオイルやジェルなどの開発にも携わっている、木村淑子さんのセラピストライフを紹介します。
大阪市北区南森町は、大阪最大のターミナル駅・梅田駅から一駅の場所でありながら、とても落ち着いたエリア。
警察署や裁判所、造幣局などの官公庁施設が集まっている町です。
サロン「salon de lumiere(サロン・ド・ルミエール)」で木村さんが提供しているのは、アロマセラピーやスウェディッシュマッサージ、リンパトレナージュ、ロミロミマッサージ、リメディアルマッサージなどのオイルトリートメントを、彼女の経験のもと組み合わせたパーソナルメニューです。
何気ない会話の中で主訴を聞き取りながら、お客様も気付いていない身体の変化に合わせてメニューを組み立てているそうです。
「看護師の頃にアロマテラピーを学び始めて以来、セラピーが楽しくなっていくつものスクールで勉強させていただきました。ボディーの学校でいえば4、5校は出ているんです。だから、いろいろな手技を組み込んだオリジナルセラピーとなっています。基本の流れはありますけど、『来るたびに手技が違う』と驚かれないように、お客様には『細かな手技はちょっとずつ変えています』とお伝えしています」(木村さん談)
現在は、平日にJ-LABOで商品開発と販売に携わっているため、サロンは土日限定で1日2人までというスタイル。
少ない枠であるため、リピーターさんだけをお迎えしている状況なのだそうです。
中にはサロンのオープン当初から通っているリピーターさんもいるとのことで、心身のメンテナンスとして、お客様から頼りにされているようです。
看護師だった木村さんが、なぜサロン経営と商品開発の2つの道を歩むようになったのか。インタビューのなかで伺うことができました。

アロマって“おまじない”じゃないんだ
警察官のお父様を持つ木村さんは、幼い頃は「ちゃんとしていないと」と自分に言い聞かせるような、変に正義感の強い子供だったと、笑いながら話してくれました。
ただ、彼女が進んだのは親に勧められた警官ではなく、看護師。
高校時代に1日看護体験をしたことがきっかけなのだそうですが、看護学校に入学してからも「結構、楽しい学生生活を送った」といいます。
「看護学校の勉強は楽しかったですね。人の体のことや病気のことを学んで、医師とは違った角度から、看護師としてのアプローチとして、どんなことができるのかなと考えるのがすごく楽しくて」(木村さん談)
身体がどのように影響し合っていて、それが症状やデータとして表れているか。そして、どんなケアが有効なのか。
そうした関連を図を起こしていく授業があるそうですが、今でもカウンセリングの際には自然に、そうした関連図が頭を巡っていて、施術の組み立てに役立てているとのことでした。
「あまり明確にしているわけではないですけど」と彼女は笑顔で話してくれましたが、看護学校での経験がセラピストとしても役立っていることがよくわかります。
看護学校を卒業した木村さんが働き始めたのは、救急病棟とICU(集中治療室)でした。
重症な患者さんも多く運び込まれるという現場に10年ほど立ち続けて、「しんどかったですけど、すごくやりがいのあるお仕事でしたね」と彼女は振り返ります。
そこでの仕事を通して、木村さんは患者さんの身体のことだけでなく、その人のご家族やこれまで送ってきた人生など、深く知ることになったそうです。
そして、看護の世界でよく言われる、「ニーズがなければ看護にはならない」という言葉の意味を考えさせられる場面を何度も経験したといいます。
「ニーズがないのにケアをしても、それは押し付けであって看護じゃないわけです。1人の患者さん、1人のお客さまに、ちゃんと興味を持って、何にお困りなのか、何を求めているのか。それを見極めていくっていうのは、看護にもサロンにも通じるところなのかな」(木村さん談)
木村さんがアロマアロマセラピーと出合ったのは、看護師の勉強会でした。
「アロマって“おまじない”じゃないんだなって初めて知って、まさに目から鱗で、面白かったですね」
興味を持ち始めた彼女は、3校ものアロマアロマセラピーのスクールに次々と通い、学びを深めていきました。
彼女がセラピストの道へと進むきっかけ。それは、ニュージーランドへの語学留学でした。
当時は、一般外科や婦人科のある病院に移っていて、勤務環境が良く、休暇にはたびたび海外旅行に行っていたとのこと。
そして、「旅行ではなくて、現地で暮らしてみたい」という気持ちが芽生えだした頃に、留学中の友人に誘われ、ほとんど英会話ができない状態でニュージーランドに渡ることを決めます。
「周りに助けられながら英語で授業を受け、3ヶ月が経つ頃にようやく楽しくなってきた」と振り返る木村さん。
実は、ニュージーランドでセラピストとしての活動を始めていて、現地でポータブルベッドを調達して、アロマセラピーの出張マッサージをしていたそうです。
しかし、海外での生活に手応えを感じ始めた頃、木村さんは事故に遭ってしまい、1年の留学期間を2ヶ月残して、帰国を余儀なくされることになってしまいました。
「何しに行ったんだろう」と凄く落ち込むなかで、次のことを考えたときに彼女の目に映ったのは、セラピストとして活躍するセラピースクールの同期たちの姿でした。
「自分も開業したいな」と思いつつも、「看護師しかしたことがない私に集客とかできるかな」と逡巡した結果、彼女が出した答えが、「看護師を生活のベースにしながら、京都の実家にサロンを作る」というものでした。
こうして、2013年に実家の1室を施術用に準備し、看護師の仲間やその知人を招くという形で、サロンをオープンさせたのです。
看護師と自宅サロンというスタイルで、2年ほどセラピストライフを歩んだのですが、その後の2015年に大阪市南森町にサロンを持つことになります。
私が「なぜ、実家のサロンから出たの?」と訊くと、「夕食時になるとカレーとか煮物の匂いがして」と木村さんは笑いながら教えてくれました。
「実家でやっているというとこもあって、夕食の時間が近づくにつれて、料理の匂いが漂ってくるんですよ。アロマサロンなのに。お客様は『気にせんでいいよ』『いい匂いやね』と笑ってくれるんですけど、私自身は申し訳なくて。だから、やっぱり独り立ちしようって思って、サロンを出せる物件を探しました」(木村さん談)
木村さんは京都生まれですが、高校から就職までずっと大阪で生活していたこともあり、ターミナル駅である梅田駅から一駅で、徒歩5分の物件に目を付け、一念発起してサロンを再オープンさせます、
それが、現在の場所「salon de lumiere(サロン・ド・ルミエール)」です。

サロンに来てくださるお客様がいるかぎり
時を同じくして、木村さんのセラピストライフにもう一つの展開がありました。
あるビジネス交流会で、「僕は科学者で、油脂の研究を25年しています」と話す人に出会ったのです。
当時、アメリカのアロマテラピーを勉強中だった木村さんは、アメリカには窒素充填で酸化を防いだ精油があることを思い出し、「手のひらサイズの窒素充填機は作れないものですか?」と何気なく聞いたそうです。
すると、それが科学者の発想を刺激することになります。
最近ではすっかりお馴染みになりつつある「ウルトラファインバブルの洗浄器」がありますが、その技術を応用して、キャリアオイルなどに水素ナノバブルを封入して還元作用を持たせた粧材が作られたのです。
そして、商品を開発し特許を取得することになり、気づけば木村さんも開発のアドバイスと販売を手がけるような立場になっていました。
「その科学者さんが代表をされているJ-LABO(ジェイラボ)という会社は、もともと技術コンサルの会社だったんです。『企業のお悩みを聞いて化学で解決しますよ』という会社です。私は最初、『いいものができたら、私が一番のお客さんになります』っていうスタンスだったんです。それが、『自社での商品開発や販売は初めてだから一緒にやろう』と誘っていただけたんです。気が付いたら、良い意味で巻き込まれていたって感じです」(木村さん談)
看護師とサロン経営と J-LABOの仕事。それらが重なり、忙しくて、自分自身の体のケアも疎かになっていくなかで、木村さんは仕事のバランスに悩んだそうです。
結果的に徐々に看護師としての仕事を減らしていくことになったのですが、サロンにお客様を招く時間が安定しないことも、彼女の悩みでした。
それをJ-LABOの代表に相談すると「サロンに来てくださってるお客様がいる限りは、絶対続けた方がいい。原点は絶対あった方がいいよ」とアドバイスをもらったそうです。

そして、J-LABOとの両立ができるように協力してくれると答えていただけたのです。
「私はセラピーが大好きです。これがなくなったら、私は自分の原点を見失ってしまうかもしれないし、開発した粧材を使ってくれるセラピストさんの気持ちが分からなくなってしまうかもしれない。だからこそ細々とでも続けていきたいと思います」(木村さん談)
木村さんにセラピストとして大切にしているを尋ねると、彼女は少し考えた後、私の目を見て一言、「否定しないことです」。
「せっかく作ってくださったサロンの時間なのだから、『いい時間だったと』思っていただきたいんです。それには施術だけではなくて、会話のなかの何気ない一言だったり、接客態度も大切だと思うんです。たとえば、お客様が口にした言葉は、その方にとって今はそれが正解なんです。それを私が否定してしまったら、きっとモヤッとした違和感が残ってしまう。私にできるのは、おっしゃることを受け止めて、施術で返すしかないんじゃないか。そんなふうに思っているんです」(木村さん談)
セラピストは健康に関する知識を一般の人よりも知っているため、お客様につい自分の視点から見える「正しいこと」を伝えたくなりやすいものです。
しかし、サロンで漏れるお客様の言葉は、実は弱音だったり、悩みだったりがその背景にあることが少なくありません。そして、多くの場合、それは「正論」で返されたくないような、あるいは家族や友人にも言えないような、ナイーブな問題が隠れていたりします。
サロンの居心地の良さは、セラピストの技術だけではなく、お客様が眠れるほどに「安心な場所」と感じられることもとても重要です。
だからこそ、否定されないこと、言い換えれば、ここに居て良いのだと「受け入れられていること」は、ときに技術以上に大切な、お客様にとっての「サロンの価値」になります。
木村さんは自分のサロン経営を「細々と」と表現しますが、10年近くの間、通い続けているお客様がいるというのは、そこにはそのお客様にとって他には替えがたい価値があるということです。
お客様をまず受け入れ、ニーズを読み取り、適切な提案をする。きっとそれは、看護の世界とも通じる大切なことなのでしょう。
「私はお客様の近況を聞かせていただくのを、いつも楽しみにしているんです。ついついお話が弾むんですよ。きっと年月が経てば、私もお客様もライフステージも身体の状態も変わっていくと思います。それを、お客様と一緒に楽しんでいきたいし、一緒に歩んでいきたい。一緒に寄り添わせていただけたら、すごくありがたいですね」(木村さん談)
良い意味で巻き込まれて始まった粧材開発と、自ら望んで作ったサロン。
その2つが合わさってこそ、木村さんの今のスタイルがあり、そしてそのバランスはこのスタイルを肯定してくれる人たちに支えられてるのです。
きっと、年月が経つにつれて、また新しいスタイルを生み出していくのでしょう。
その姿は、また次世代のセラピストにとって、ロールモデルの1つになっていくはず。そんな未来を思い浮かべつつ、インタビューを終えました。

校長からのメッセージ
今回は、サロン経営と化学企業での粧材開発に携わっている木村淑子さんにお話を伺いました。
彼女が勤める J-LABOは、昨年の11月に開催された「セラピーワールド東京」(株式会社BABジャパン主催)に出展しており、そのイベントに私も講師として登壇したことがご縁となりました。
自分たちが施術で使う粧材を、セラピスト自身が作る。経済合理性では後回しにされそうなこだわりや、表面化されていないニーズを製品に生かすという試みは、 J-LABOさんを含めて、徐々に見られるようになってきました。
1つの地域では少ないユーザーでも、日本全国でみれば、あるいは世界規模でみれば、ビジネスとして成り立ちやすくなるというわけですが、それはやはりインターネットや配送システムの発展の恩恵の1つなのでしょう。
また、木村さんのように、企業とサロンの両立させるスタイルがみられるようになったのも、最近の流れでしょうか。
「サロン一本で生きる」あるいは「系列店を増やす」は、セラピストの生き方の1つですが、それだけが生き方ではなくなってきたのです。
企業とサロンの組み合わせだからこそ、新しい価値や合わせ技が生み出されることもある。
「セラピー×○○」のように、異業種や別のスキルとの組み合わせが、新しいスタイルとなることもある。
セラピストが持っている「当たり前」が、実は企業にとっては「発見」や「気付き」であり、結果的に新しい製品やサービスが世の中に送り出される、というパターンを散見しますし、これからも増えていくのかもしれません。
さて、本編は木村さんのセラピストライフを中心にご紹介しましたので、ここでは木村さんが考える新しいオイルの可能性について、少しだけ触れておきたいと思います。
「例えば、摩擦係数だったり、浸透力だったり。そういう角度からセラピーとオイルの関係を突き詰めてみきたいですね。今まではオイルの成分が注目されてきたと思うんですけど、マッサージの圧の強さによって適してるオイルは違うのではないかと。日本人と外国人とでは肌が質が違うし、性別や年齢でも、血管の太さや筋肉量の関係で適したオイルはきっと変わってくるはずです。これからは、そういったものを研究していきたいと思います」(木村さん談)

たとえば私自身、年齢を重ねるなかで、肌質も筋肉量も、体脂肪率も変わってきていて、ならばマッサージオイルがずっと同じがよいとは限りません。
女性が年齢によって化粧品を変えていくように、マッサージオイルにも変化があってもよいのかもしれません。
こうした研究は、20年以上の日本のような、まだまだセラピスト人口が少ない時期では難しかったはずです。
ですが、セラピスト人口が増え、またインターネットで繋がりやすくなっている現在だからこそ、数値的なエビデンスは以前よりもずっと得られやすくなっているはずです。
こうした研究もさることながら、木村さんが商材開発へと「巻き込まれる」ことができたのは、やはり看護師として医学的な素地があるからではないしょうか。
それが、実は科学者さん( J-LABO代表)と意見交換するための橋渡し的なリテラシーになっていたのかもしれないのです。
そう考えると、セラピストライフとはやはり不思議なものだと、今回もまた思い至るのでした。
サロン
https://aromatologist-lumiere.webnode.jp/
ORIINA