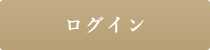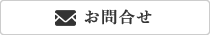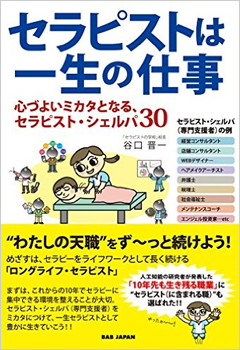- ホーム
- セラピストニュース&コラム
- 谷口校長コラム
- 上前拓也さんのセラピストライフ~個人コーチング
上前拓也さんのセラピストライフ~個人コーチング
2022/08/08
北海道札幌市にて13年にわたって合同会社友歩(ゆうほ)を運営し、個人を対象にしたコーチングや、企業での研修講師、後進のコーチ・講師の育成などをしている、上前拓也さんのセラピストライフを紹介します。
【企業研修編】はこちら
【育成講師編】はこちら
上前さんは札幌を拠点に、個人を対象にしたコーチングのセッションを行っています。
ただ、オンラインセッションを中心にしてるため、お客様は北海道内はもちろん、全国にいるそうです。
お客様の傾向を聞くと、上前さんが企業研修に携わっていることもあって、ビジネス関連の相談が多いとのこと。
経営者の方なら企業の業績アップのために、会社員の方であれば仕事でのステップアップのために、あるいは将来的に起業を目指して、上前さんのセッションを受けるそうです。
セッションを受ける期間としては、上前さんは最低でも3ヶ月をお勧めしており、半年〜1年ぐらい継続する方も多いそうです。
中には、開業初期からのお客様もいて、上前さんいわく「今やコーチングというよりも、月に1回のリフレッシュになっているのかもしれません」とのことです。
コーチングについての説明を求めると、「その人の持つ目標や願望を、その人自身の力で達成をするためのコミュニケーションサポートですね。なんか教科書的な感じですけど」と、上前さんは笑顔で答えてくれた後、コーチングの手法の1つである「頭の中の整理」を、探し物に喩えて説明してくれました。
「自分の部屋に喩えると、部屋の中に必ずテレビのリモコンがあるはずなのに、散らかっていてリモコンが見つからないってことがありますよね。でも、1つずつ片づけていったら、いつかはリモコンが見つかるはずなんです。コーチングもこれと同じで、本人の中に答えあるはずなのに、頭の中がゴチャゴチャになっていて気付いてないことがあります。ゴチャゴチャしたものを1つひとつ整理していくことで、自分の中の答えに辿り着くことができるはずなんです」(上前さん談)
実際、自分の頭の整理をするのは、1人だとなかなか難しいものです。
自分1人で考えるよりも、考えを口に出し、それに対して何かしらの反応が返ってくることによって、自分の考えを整理しやすくなるわけです。
もちろん、話し相手によっては、余計にゴチャゴチャを混ぜ返してしまったり、都合の良い方向にミスリードしてしまったりしますし、2人ともが悩み込んでしまって一向に答えに辿り着けないなんてこともあるかと思います。
だからこそ、コーチングという手法が有効になるのであり、コーチとは「話し相手としての教育を受けた人」ということになるのではないでしょうか。
上前さんによると、ビジネスで業績の数字を求めている経営者が、コーチングを受けたことで、「まず社内の人間関係を先に整えた方がよく、数字は後々付いてくるはず」と考えが変わったこともあるそうです。
頭の中の整理ができて、取り組むべき課題の優先順位が見えたということでしょう。
上前さんに、コーチとして活動し始めたきっかけを訊くと、「実は、システムエンジニアをしていた頃に、副業として始めたんです」と以前のことを振り返ってくれました。
相談者本人が自分で感じている以上に信じること
上前さんは工業系の高専校を卒業した後、道内の大手企業でエンジニアとしてシステム開発などに従事したそうです。
その仕事の一方で、2005年ごろから副業でインターネットを通じて悩み相談を受け始めます。
今でこそ、オンラインセッションやオンライン講座は珍しくありませんが、インターネット環境としてはADSL回線が普及して「ブロードバンド元年」と言われるのが2001年で、家庭用「光ファイバー回線」の登場が2003年。付け加えると、動画サイト「Youtube」がアメリカで誕生したのが2005年のことでした。
この時期にインターネットでの悩み相談を開始したというのは、オンラインセッションの最初期の事例だろうと思います。
実際、SEである上前さんはWEBカメラを持っていても、相手はそれを持っていないため、上前さんは動画で、相手は音声や文字でやり取りする状況だったそうです。
SEという仕事と、悩み相談の間には、大きなギャップがあるように思えます。
その疑問を尋ねると、「ずっとSEだけでは生活できないだろうと思っていて、いつか独立したい気持ちもあった」と上前さんは言います。
インターネット環境の変化はめまぐるしく、新しいプログラミング言語が次々と生まれていると聞きます。
上前さんも、「頭の回転とかを考えても、若い人には絶対勝てなくなるので、SEでの独立は全く考えてなかった」とのことでした。
では、なぜ「悩み相談」だったのかと言えば、上前さんは学生の頃から人の相談を受ける機会がなぜか多かったそうです。
また、「インターネットでの悩み相談」というサービスが他になく、インターネットの発展によってそれが可能になったことも、その理由であるようです。
「なぜか昔から人から相談される事が多かったですね。いわゆる相談しやすい空気感はあったのかもしれません。ただそれは、今も自分のコーチとしての特徴の一つだと思っています」(上前さん談)
しかし。こうした始めた副業の中で、人知れず悩みを抱える人たちに接し、当時の上前さんは相談を受けるテクニックが不足していることを痛感することになります。
そして、「ちゃんとした悩みの受け方を勉強したくなった」と、上前さんはコーチングとカウンセリングを学び始めたそうです。

このコーチングやカウンセリングといったコミュニケーションスキルは、上前さんが営業職へ移っても力を発揮し、好成績を収めることができたということでした。
上前さんが合同会社 友歩を設立し、コミュニケーションスキルを使ったサービスを本格的に開始したのが、2009年のこと。
当初はカウンセリングも行っていたそうですが、前向きな人を支援したいという気持ちが次第に強くなっていき、コーチングをメインにするようになっていぅたそうです。
また、個人客を対象としたBtoC(Business to Consumer)のサービスだけでなく、企業を対象としたBtoB(Business to Business)のサービスも視野に入れていたことも、コーチングをメインにした理由の1つだったそうです。(【企業研修編】参照)
開業当初は、BtoCのお客様が多かったとのことでしたが、現在の活動の多くはBtoBであり、BtoCのお客様は少人数に制限しているとのことでした。
「BtoCの場合、体1つでは限界があるので、経営的にも、また僕自身の志向としてもBtoBの仕事を増やしていきました。ただ、やっぱり個人と向き合っていないと感覚が鈍ってしまうので、現場から離れてはいけないと考えています。今、ちょうどいいバランスなので、今のクライアントに対して最善を尽くしていきたいですね」(上前さん談)
個人を対象にしたコーチとして大切にしている事を訊くと、上前さんは笑顔でこう答えてくれました。
「一番大切にしてることは、その人の力を100%信じることです。もうそれに尽きると言っても過言ではないです。相談者本人が自分で感じている以上に信じること。それが一番大事かなと思います」(上前さん談)
そう語る上前さんの声と表情には、心からの確信が感じられました。
コーチが相手以上に相手を信じる。それは、セラピストがお客様の生命力を、お客様以上に信じていることと、よく重なります。
コーチやセラピストの確信が強いほど、お客様も自分を信じられるようになっていき、能力をより発揮できるようになっていく。それは、集団を作って生きる人間だからこそ持つ、特徴の1つなのかもしれません。
校長からのメッセージ
現在、上前さんの個人セッションは、1回1時間で、料金はオンラインの場合は1万円ほどで、対面の場合は2万5000円ほど。
個人のお客様の数は少なく抑えているとのことですので、上前さんの活動全体で見れば、企業を対象にしたBtoBの方が割合的にはかなり大きいはずです。
それでも、個人を対象としたBtoCを続けているのは、1対1でのコーチングの現場から離れないことの大切さを、彼が知っているからです。
加えて、後進の育成をする立場としても、現在進行形で個人に向き合い続けることが大切にしているようです。
コーチングを受ける方たちの傾向も時代とともに変わっていくでしょうから、そうした変化を肌感覚で知っておくことは、育成においても、BtoBの活動においても、必要なことなのだろうと思います。
そういった意味では、上前さんはとてもバランスよく活動をしていることが分かります。
さて、今回、コーチングのプロフェッショナルである上前さんにお話を伺ったわけですが、ふとコーチングとカウンセリングの違いについても気になりました。
実際、上前さんにコーチングの依頼に来る人の中にも、カウンセリングを受けた方がよいと思われる方がいるそうです。
「相談者の多くは、目標に向かって進もうとしているので、心の状態はプラスだといえます。ですが、相談者の中には心の状態がマイナスの方も希にいます。それはカウンセリングが必要な状態なのですが、本人としてはカウンセリングを受けることに抵抗があるようなんです。僕がやってるのはコーチングっていう名前なので、受けやすいという面もあるようです。弱みを見せるのが苦手な方なのかもしれませんね。」(上前さん談)
コーチとして活動している人の中には、カウンセリングが必要な状態の方に対して、自らの手法で無理やりプラスに引っ張り上げようとすることもあり、上前さん自身は一人ひとり相談者を見極めているとのこと。
コーチングとカウンセリング。あくまでも日本での認識になると思いますが、自分の思考力だけでは整理が付かない状況で、外から手助けするという意味ではよく似ています。
上前さんが喩えてくれた「散らかった部屋で探し物をする」という場面でいえば、捜し物が「リモコン」であることが分かっている場合は、コーチング。一方で、何を探していいか分からない状態ならば、おそらくカウンセリングなのではないでしょうか。
上前さんのようにビジネスシーンでは、業績アップが主な目標なので、コーチングが適していると言えそうです。
ただ、その目標を見失っている場合、とくに本人のモチベーションが低下している場合は、カウンセリングになるのかもしれません。
翻ってセラピストの場合、カウンセリングという言葉をよく使いますが、コーチングを明示して使う場合は多くはありません。
お客様は「探し物が何か分からない」状態でサロンに来て、セラピストのカウンセリングを通して「探し物の正体に気付く」というプロセスがあるのではないでしょうか。
そして、セラピーには、お客様を元気づけて、前に進ませる力もあると考えています。
つまり、コーチング的な能力もまた、セラピストには求められるのでしょう。
もしかすると、現役で活躍しているセラピストたちには、ごく自然にコーチングができている人もいるのかもしれません。
今後、活動を始めたいセラピストや、能力を磨きたいセラピストにとって、こうした視点は良いヒントになるのではないか。そんなことを考えたインタビューでした。
認定講師養成講座
笑顔の研修製作所
教育技術スペシャリスト養成講座