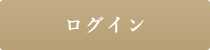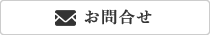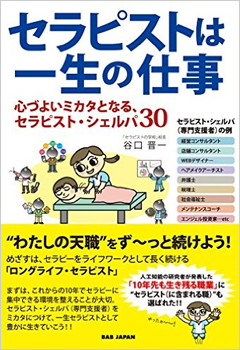- ホーム
- セラピストニュース&コラム
- 谷口校長コラム
- 小松ゆり子さんのセラピストライフ〜ディレクター型シェルパ
小松ゆり子さんのセラピストライフ〜ディレクター型シェルパ
2021/11/17
東京南青山にて、個人サロン「corpo e alma(コルポ エ アルマ)」を運営し、オーダーメイドの施術と、セラピストの育成、さらにセラピー関連事業やイベントに協力する「シェルパ」としての活動もしている、小松ゆり子さんのセラピストライフを紹介します。
【個人サロンセラピスト】編はこちら
【育成セラピスト】編はこちら
小松さんは、南青山の個人サロンの運営の他にも、セラピストが主催する協会やイベント、スクールなどの運営にも携わっています。
彼女の活動は幅広く、企画立案やディレクション、ブッキング、調整役のような裏方もすれば、動画やイベントで司会進行役として顔を出す、いわば“出役”としても立ち回ります。
本稿では、依頼主の示す方向性に沿って、具体案を考えたり、仕事の割り振りなどをすることから、彼女の活動をひとまず「ディレクター」と呼ぶことにします。
私はセラピストの活動を支援する専門家を「シェルパ」と呼んでいるので、小松さんはディレクター的な働きをしてくれるシェルパといえます。
カルチャー枠で語られるようなセラピスト業界に。
彼女の活動を総じて言えば、「セラピー業界を発展させるためのプロジェクト」です。そのために、団体や協会の垣根を越えて飛び回っています。
普通であれば自分のサロンやスクールの運営で手一杯だし、協会や団体に属していればその拡大にだけ注力しそうなものです。
ですが、小松さんは「セラピー業界の発展」を視野に入れて活動しています。
なぜ、そのような活動をしようと考えたのかと疑問に思い、小松さんに聞くと、このように答えてくれました。
「セラピストは文化・健康にも関わる面白い仕事です。でも、セラピスト業界は、全体的に低賃金の肉体労働になっている。セラピスト業界が発展して、カルチャー枠で語られるようにならないと、自分も含めて未来はないと、この業界に入った時から思ったんです」(小松さん談)
一部で盛り上がるだけのマイナーなカルチャーが、社会的に通用するメジャーな位置づけになった好例として、小松さんは自身が前職の音楽業界で携わっていたジャパニーズ・ヒップホップ・カルチャーについて話してくれました。
最近ではヒップホップのアーティストが国民的歌番組などに出場することも、楽曲がCMなどで流れることも珍しくなくなりましたが、まだ黎明期であった2000年代初頭のこと。
その頃いち早くブレイクした、Dragon AshのギターボーカルのKJこと降谷建志さんは、レーベルの枠を超えてまだ知られていないアーティストを積極的に呼ぶイベントを開催していました。
そのイベントを経て、小松さんが関わっているアーティスト達が続々と注目され、売れていった経験があるそうです。
そうやってメジャーになるアーティストが増えることで、ジャパニーズヒップホップは、日本の社会・文化の中に定着していったわけです。
「自分が良いと思うものを、より多くの人に知ってもらいたい」というシンプルな思いが、カルチャー・シーン全体の底上げをした、という好例です。
こうした流れの中に身を置いていた小松さんは、セラピストになってすぐに、セラピスト業界全体をメジャー化することの重要性と必要性を強く感じたわけです。
そして、業界が発展することで、彼女自身のセラピストライフも未来が拓けるはずだと考えたのです。

これからも巻き込まれながら転がり続けるんでしょうね
小松さんは、知的探求のために様々な学びの場に出ていく中で、協会や団体の枠を超えて人脈を広げていました。
さらに、音楽業界のプロモーション職出身であることで、様々なセラピストからプロジェクトへの協力オファーを受けるようになりました。
そして、裏方として協力しているうちに、いつの間にかオンラインイベントの司会進行まで任されるようになり、最近はセラピー業界内ですっかり顔の知られる人物になっています。
小松さんがディレクターのように活動する上で大切にしていることを聞きました。
「プロジェクトを進めていくためには、“情熱大陸な人”と“平熱大陸な人”が両方いないといけないと思っています。プロジェクトを発案する人の多くは“情熱大陸な人”なので、私は“平熱大陸な人”として、周囲を見ながら、状況を把握してバランスを取ることを意識しています」(小松さん談)
また、小松さんは、出来ないことをはっきりと伝えることも大切にしているのだそうです。
出来ないことまで引き受けることは、自身の負担になるだけでなく、プロジェクトが停滞する要因になることを知っているからです。
こうした感覚も、音楽業界で大人数でプロジェクトを進めてきた経験値が活かされているのでしょう。
「これからも巻き込まれながら、転がり続けるんでしょうね」と笑いながら話す小松さん。
自分の出来ることを粛々とこなしながら、セラピスト業界の発展を願って活動をしていくそうです。

校長からのメッセージ
イベントの企画・実行でも、スクールや協会の立ち上げでも、どんなプロジェクトも立案者1人の熱量だけでは前には進まないものです。
そこに、1歩引いた位置に立って適切にアドバイスをしたり、課題を明確にできる人物がいるとプロジェクトは着実に前に進んでいきます。
戦国時代で言えば、総大将の側にいる軍師ともいえる存在。
セラピスト業界では、多くのセラピストが自分のサロン運営についての経験値はあっても、大きなプロジェクト全体を見渡して意見が言える人間は少ないように思えます。
その少ない中の1人が、今回インタビューした小松さんです。
小松さんの場合、「自分がセラピストとして生きていくこと」が発想の根源にあるようですが、その発想を深めた結果、セラピスト業界全体を俯瞰するというところにまで視野を広げています。
だからこそ、日本におけるセラピスト業界の現状と将来について俯瞰して見ることができて、その上で自分が関わるプロジェクトが掲げる理想と現実の間をつなぐ役割もこなせるのでしょう。
もちろん、ディレクター的な立場にあっても、「楽しいからやれる」という彼女のスタンスは変わりません。
無理なもの嫌々することの効率の悪さも、それが自分自身にウソをつくことなることも知っているからだと思います。
「利己的な自分を否定しないで、関わるプロジェクトの中で楽しさを見つけるようにしています。大変だけれども、知的好奇心が満たされれることがご褒美になるし、自分が良いと思うものをたくさんの人に知ってもらえることも嬉しいんです」(小松さん談)
思い返せば子どもの頃、オススメの本やCDを友達に貸した記憶は誰にでもあるはずです。
そこに邪念はなく、純粋に自分が好きなものを知ってもらう喜びがあります。そして、友達がそれに共感して「好き」と言ってくれたときには喜びは倍増するものです。
こうした心理は、共同体をつくるヒトという種に備わる根源的な喜びの1つであり、またヒトの行動を後押しする衝動(パッション)である気がします。
Dragon AshのKJさんが熱い衝動(パッション)で行動したように、小松さんは静かな衝動(パッション)に突き動かされているのかもしれません。
「セラピーはアート」と言われることがあります。また、古来よりアート(芸術)はセラピーのツールとして活用されてきました。
セラピーは「癒す」ことを目的とする中で「心地よさ」を探求し、「好き」「楽しい」「うれしい」というような感覚や感情を大切にする側面がある文化なのです。
ならば、それが定着した社会はきっと楽しくて、嬉しいものになるはず。そんな夢想を思わず掻き立てられるインタビューでした。
YURIKO KOMATSU